アケビコノハとは?

| 分類 | 鱗翅(りんし)目ヤガ科 |
|---|---|
| 学名 | Eudocima tyrannus |
| 和名 | アケビコノハ |
| 分布 | 日本全国 |
| 中国・台湾・東南アジア・インドなど |
幼虫はアケビを食べ、成虫は枯れ葉そっくり
| 寄生植物・食草* | アケビ科(アケビ・ムベ・ミツバアケビ)など |
|---|---|
| ヒイラギナンテン | |
| アオツヅラフジ |
アケビコノハは、成虫が枯れ葉(コノハ)そっくりの見た目をした虫の代表例で、和名の由来は、成虫の見た目と、幼虫の食べ物がアケビの葉であることです。枯れ葉そっくりの虫は、ほかにもコノハチョウやカレハカマキリなどが有名で、蛾のなかではアケビコノハと同じヤガ科にアカエグリバがいます。
山野や民家で観察できる
| 幼虫の寄生植物 | アケビ・ムベなど |
|---|---|
| 成虫の飛来植物 | 食用の果樹・ツバキ・フジ・クリなど |
| 観察場所 | 平地~低山地にある林・公園・民家 |
| 観察時期 | 5~10月ごろ |
| 越冬形態 | 成虫(例外あり) |
アケビコノハは日本全国に分布しており、幼虫はアケビの生えている場所で観察でき、アケビが自生している山や野のほか、都市部の民家や公園にもいます。観察できる時期は5月ごろ~10月ごろで、繁殖期は年に2~3回あり、晩秋までにはすべてが羽化を終えて成虫で越冬するのが基本です。
果樹農家では害虫として知られる
アケビコノハの成虫は、果樹農家では果汁を吸う害虫の1つとして知られており、駆除対象です。アケビコノハは夜のうちに果汁を吸いに来て、吸われた果実は数日たつと腐ってしまい、出荷できません。果実は、りんご・なし・もも・ぶどうなど全般であり、熟れてきて出荷が近いものを特に吸います。
防除は、「園全体に網をかける」「光を嫌う習性を利用して照明をつけておく」などです。
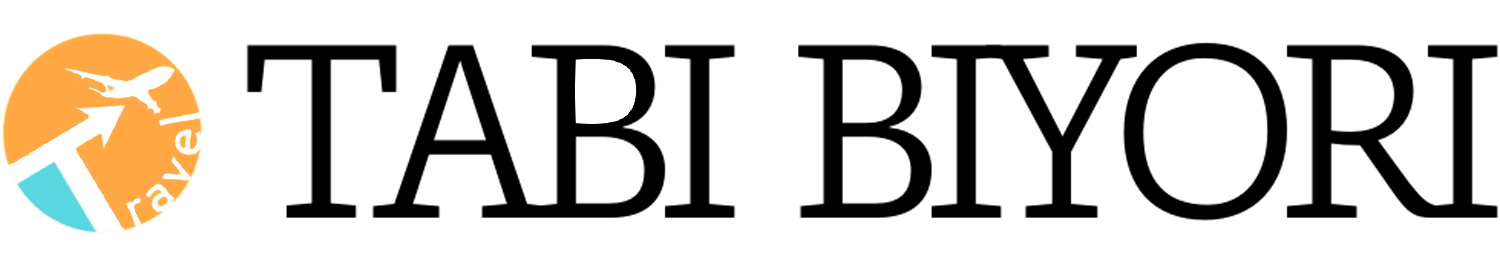







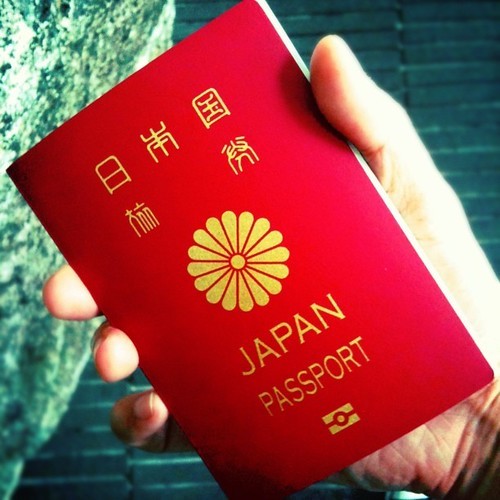








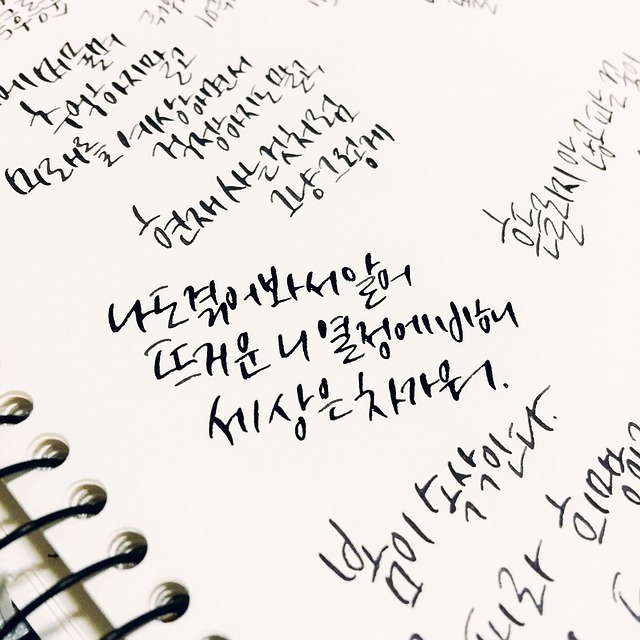




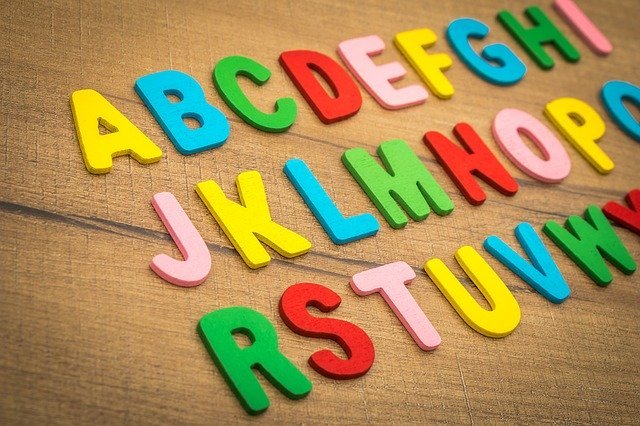


















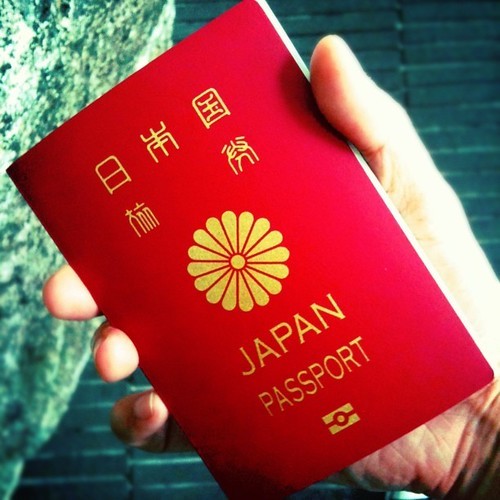



アケビコノハってどんな虫?